京都府生まれ。写真は「あすなろ園(心身障害児通園施設)」に勤務の頃の勇姿。24歳から44歳まで交野市。この園で関わった子どもたち、母親、先生たちから、人生で大事なことのすべてを学んだ。

45歳から、同志社女子大学、児童文化研究室へ。学生たちの苦悩の深さを知る。物語が人を支えるところを日々実感。70歳、退職。下は古希の写真。若き面影がなくなる老いも良いものだと思う。


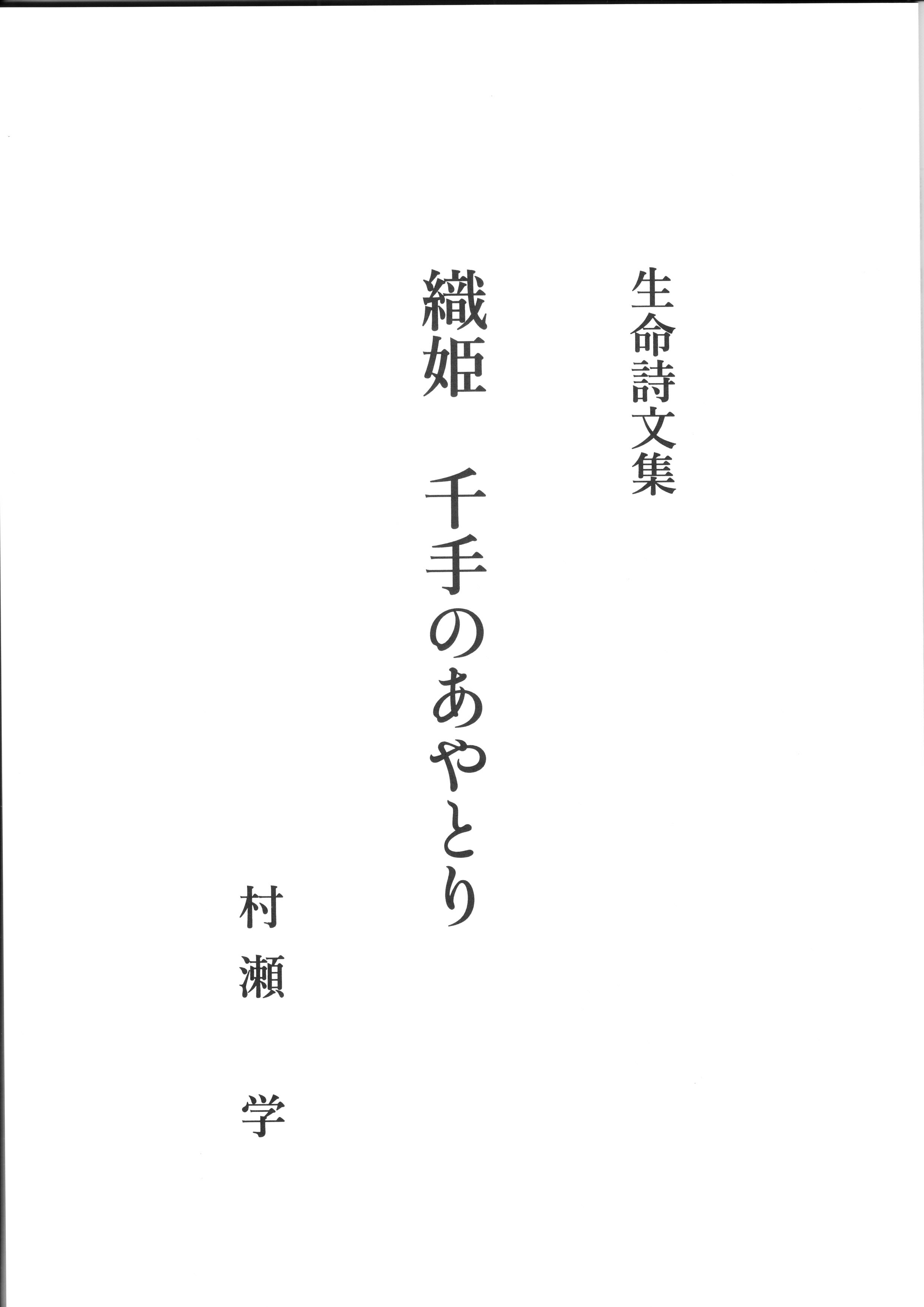
『生命詩文集 織姫 千手のあやとり』というタイトルの、詩集のようなものを刊行いたしました。でも通常の詩集というのとだいぶ違います。たぶん、初めて試みられた構成の珍しい詩文集、という体裁の詩集です。PFDで読みづらいですが、別途お届けいたします。上の赤い帯状の『生命詩文集 織姫 千手のあやとり』と書かれた所をクリックしてみてください。少しめくってみられて、関心がわいて、冊子の形で読んでみようかなと思われた方は、終わりの方の「PDF編集後記」をお読みください。冊子の購入方法を書いておきました。めんどくさい方は、このPDFをコピーなさってください。近年、詩集になった本は高価なものが多く、スマホ料金の支払いで、アップアップしている若い人には、なかなか手を出しにくいものになっているので、今回のこの詩文集は、無料で見てもらえるように考えてきました。その意図は、この詩文集の中の「タンポポ」の詩文を見てもらうとわかるかも知れません。道ばたのたんぽぽを手にするのに「お金を払わなくてもいいなんて」という驚きが記されているからです。
ところで冊子になった詩文集には、二つ折りの「栞 小さな質問箱」という文章を挟んでおります。PDFでは一番最後に載せています。その「栞」を以下に掲載して紹介しておきますので、そこに書かれていることに興味をもってもらえた方は、本文の「詩文」を読んでいただければ、幸いです。
なお、PDF版の『生命詩文集 織姫 千手のあやとり』は、編集工房「エディシオン・アルシーブ」の西川照子さん、栗田治さんから、細かな誤字脱字、表記の間違いを指摘していただき、修正したものになっています。こんな間違いがなぜ、というようなところが、ひとりの目では、気がつかないんですね。お恥ずかしい限りです。PDF版には、その修正は反映されていますが、製本になった冊子を購入していただき、それを読まれた方で、ここは変だと思われた箇所は、PDFでその箇所を見てください。必ず修正されておりますから。それからPDFの空きになっていたページに、「千手観音」(10ページ)と「モーツアルトの手」(54ページ)の二つの詩を入れることができています。PDFの編集後記には、この追加した「二つの詩は、冊子に貼り付けています」と書いていますが、貼り付けると。冊子の重量が250グラムを4グラムオーバーし、そのために、送料が一気に310円に跳ね上がることに後で気がつきました。 ですので、「貼り付け」はあきらめました。すみません。ですので、PDF版で見ていただくだけになっております。どうぞご了承ください。
なお、冊子代500円は切手でも、と編集後記に書いておりますが、100円近くの小額の切手にしていただけますとありがたいです。
「栞 小さな質問箱」
目次
1 「もっとも大事な考え方」について
2 「織姫」のこと
3 「いきもの」篇のおもしろさ
4 「赤ままの花」を歌うな、という詩
5 「あやとり」との出会い
6 「あや」の発見
7 「生命」を「千手のあやとり」として考えること
1 「もっとも大事な考え方」について
〇:「詩文集」には長い「あとがき」を書かれているのに、まだ、このような質問箱がいるんですか・・。
●:自分の書いたものの説明というよりか、こういう「詩文集」のようなものを書こうというか、書かなくてはと思った動機を、もう少しちがった角度からも、明らかにし、記録しておくことが、わたしのように、「詩」と「詩文」の間で悩んできたものたちにとっては、どうしても必要なのではないかと思ったものですから・・。
この詩文集の核心の部分は、ものすごくシンプルなところにあって、それは「根は花を、花は根を、知っている」(「根は葉を、葉は根を」でもいいのです)という、農家の人ならだれもが知っていることを「詩」のベースに据えるというものでした。この考えは、コロナ禍で退職したときに、今までのゼミ生さん達に送った「紙上最終講義 「生命のわ」から」の中で、「もっとも大事な考え方」としてお伝えしていたものです。
その「根は花を、花は根を」の考えは、この詩文集の中では、「わ(環)」として主題化されて使われています。主題化されて、というのは、おかしな言い方ですが、要は、一つ一つの「詩」が、他の「詩」と呼応し合っているように書かれているという意味ですし、一部分の詩が、詩全体とも呼応し合っているという意味でもあります。もちろん現代詩としてある多くの詩集も、内在的なつながりは意識されて書かれているのですが、この詩文集では、全編が、それぞれどこかで交応し合うことが、意図的にわかるように工夫されて書かれているというところがあるのです。(それが成功しているかどうかは別の話なのですが・・)。つまり、この詩文集全体が、「根は花を、花は根を」を体現できるように仕組まれているように・・。
そして、詩文集は四つのブロック(「しんわ」篇、「いきもの」篇、「ひと」篇、「こっか」篇)に分かれていていますが、一つ一つの詩は、詩の全体と呼応しながらも、この四つのブロックのそれぞれにも呼応するように書かれています。(もちろんその意図もうまく実現できているかどうかは別ですが)。
こういうふうに一篇の詩と、百篇の詩の全体が、「根は花を、花は根を」になっているように作られることが、この作品の大きなテーマというか、願いとしてあったというわけです。
2 「織姫」のこと
〇:もしこの詩文集の全体が、そういう「わ」としてつながっているのだとしたら、どこから、どのように読めばいいのかと思いますが。
●:もちろん、どこから読んでもらってもいいのです。最初の「しんわ」篇から読まれると、なに、これ?と思われたり、こんな「しんわ」篇が必要なのかと思われるかも知れませんから、「いきもの」篇から読んでもらってもいいのです。
ただ「しんわ」篇の「しんわ」というのは、「神話」にとどまらず、広い意味で「物語」の世界を扱っています。ですので、そこには「宗教的な世界」も含まれています。
でも、なぜそんな世界を「詩」が対象にするのかというと、むしろその分野を対象にすることが古代からの「詩」の役割としてあったと私は思っているからです。というのも、もしこの詩文集が考えているように、世界が「あや」や「あやとり」でできているとしたら、その「あや」を支える「て」や「糸」のことを考えざるを得なくなり、そこを考えてゆけば、とうぜん「織姫」の物語にふれなくてはならなくなるからです。
それは誰が試みてもそうなるように私は思います。
たとえば「あとがき」で紹介していたゲーテの「神と世界」という詩集の中に、次のような節があります。
おわりに(アンテビレマ)
つつましやかな眼差しもって見てごらん
永遠の織姫の織りなすものを
一踏みだけで千々(ちぢ)の糸が動き出し
はた織る筬(おさ)はかなたこなたへとびかって
糸と糸とが流れるように結びあう
一打ちだけで千々の結びが生れくる
これはもらい集めたものでなく
永遠(とわ)の時より経糸(たていと)をかけてきたもの
永遠の神なる良人が 安んじて
緯糸(よこいと)を投げるようにと願いつつ
(高橋義人訳)
ここを読まれると、わたしの詩文集との類似を感じる人がおられると思いますが、関係は全くないのです。ここを読んだから、わたし織姫の詩文集ができたのではなく、全くそれぞれの独立した発想から詩集は生まれています。その証拠に、ゲーテは織姫のことを書いているのは、たかだかこの十行にすぎず、このような織姫を根本に据えて世界を考えるなどということは、キリスト教の世界では許されるものではなかったからです。
わたしの方は、発想の土台が児童文化にあり、糸を紡ぐものの物語は、「眠り姫」をはじめとしてグリム童話にはたくさんありますし(ちなみにゲーテとグリム兄弟は、生きた時代は重なっていて、弟のヴィルヘルムは、ワイマールにゲーテを訪問しています)、そもそも日本の古事記の神話篇も「織姫」の世界でもありました。そして「千手」は、当然ながら仏教固有の「千手観音」から着想は得ているわけで、ゲーテとは全く関係がありません。
さらに、わたしが織姫のモチーフの重要性を改めて確認していくのは「鉄」と「国作り」との関係を調べてゆく中で、竜神にふれ、織姫にふれるという体験をしていったからで、それは篠田知和基『竜蛇神と機織姫』などの世界的な視野の元に考察された民俗学的な考察と共振する中で得てきたものなのです。
なので今日、人文の発想から世界の成り立ちを「しんわ」として考えようとする人たちなら、誰でもが「織姫」に向かうのではないかと思ったりもしています。
3 「いきもの」篇のおもしろさ
〇:しかしそれでも、「しんわ」とか「世界の成り立ち」などと言ったものには関心のない人もいるのではないかと思いますが。
●:もちろんそうだと思いますから、「しんわ」篇は飛ばして「生きもの」篇から読んでもらうのも歓迎です。わたしがずいぶん長い時間をかけて詩篇にしたかったものが、ここにあるからです。そして、ある意味では、ゲーテのメタモルフォーゼの詩篇と呼応するところがここにあると思っていますから。
もちろん、ゲーテは「アメーバ」とか「ゾウリムシ」とか「クラゲ」とか「血液について」とかいうようなものについて書いているわけではありませんが、軟体生物の豊かさにこそ生命の源泉があるのではないか、と考えるわたしの思いは、ゲーテが求めていたものと通じているのではないかと思っています。
ところで、こういう「いきもの篇」を描いた背景には、たくさんな図鑑や大百科、博物誌から教わった目もくらむような豊穣な生きものの世界があります。(最新の美しいカラー写真は、生命体の驚愕の造形を見せてくれていますから、これらの「詩文」にも、カラー写真は望めないにしろ、イラストでもいいので、いきものの図版が添えられていたらどれほどいいだろう・・と思いました。)でも今では、ユーチューブなどで、生き物の動く映像がいつでも見られますから、この「詩文集」に合わせて見ていただけると、とてもありがたいです。
わたしが学生だった1970年代は、大学闘争と並行してテレビで「野生の王国」などが放映されていて、そういうものを見て育ったわたしなどは、人間の世界以外に生き物たちの豊かな世界があることを、十分に教えてもらった世代になります。(学校からではなくテレビからということになりますが)。
その後各テレビ局が次々に独自に「自然と生物」関係の番組を放映することになり、わたしなども録画できる頃には、ことごとく録画して見てきたと思っています。中でも、これは必見だと思ってきたのは、NHK「ミクロワールド」という5分の番組(60回分)です。わたしはこの番組をどれだけ繰り返して見たでしょうか。(番組は「ミクロワールド公式ホームページ」でいつでも見られます)。このあまりにも奇想天外で豊穣なミクロの世界。わたしのちっぽけな常識がことごとく吹き飛ばされていった世界を、見ておられない方はぜひご覧下さい。
この、電子顕微鏡でしか見られない世界を、これでもかと見せてくれる映像がなければ、私はこの「詩文集」を構想することが出来なかったと思います。かつてこういう映像は、高価な電子顕微鏡を有する大学の研究者にしか見られなかったのでしょうが、お茶の間で、小学生でも観ることができるようになっています。番組の制作者に感謝です。1回5分がいいです。1回分見ただけで、お腹がいっぱいになるからです。
それに加え、近年次々に出版されてきたたくさんな美しい図鑑たち。ここにも粘り強い撮影者と、高性能カメラ、電子顕微鏡などが活躍し、見たことのない世界を見せてくれていました。動植物の形態学、メタモルフォーゼに深い関心を寄せ続けていたゲーテが、これらの映像をみたらどれだけ喜んだだろうと思いましたね。
そして「人間」を取り巻くこうした「ミクロワールド」や「生きものの世界」を見て感じた驚きを、どうしたら表現できるのだろうかというのが、その後のわたしの「課題」となってゆきました。というのも、こういう世界に「現代詩」は、まったく無関心のように見えていたからです。現代詩は、こうした自然と向き合うことから、ずいぶんと遠いところへ来てしまったのか、それともただ背を向けて見て見ぬ振りをしてきたのか・・。そんなものは「現代詩」のテーマにはならないと思われてきたのか・・。
4 「赤ままの花」を歌うな、という詩
〇:「自然」と向き合わない詩ということで、何か気になった詩はあったのでしょうか。
●: 大学闘争の最中に読んでいた詩に、中野重治(1902-1979)の「歌」(1926年初出24歳)の詩があり、この当時は、そうだそうだと、とても感じ入った記憶があります。
歌 中野重治
おまえは歌うな
おまえは赤ままの花やとんぼの羽根を歌うな
風のささやきや女の髪の毛の匂いを歌うな
すべてのひよわなもの
すべてのうそうそとしたもの
すべての物憂げなものを撥(はじ)き去れ
すべての風情を擯斥(ひんせき)せよ
もっぱら正直のところを
腹の足しになるところを
胸元を突き上げて来るぎりぎりのところを歌え
(略)
戦中、戦後を通して、貧困や階級といった「生活苦」に取り囲まれている現状があって、それを何とか打開することが急務であり、そこに向かい合わないで、「赤ままの花」や「とんぼの羽根」などを歌っていてどうするんだという怒りがこの詩を書いた中野重治にあり、その「怒り」に若いときのわたしも共感していたと思います。
しかし、社会で仕事をするにつれて、「腹の足し」になるものとは、「思想」や「心の糧」だけではなく、現実に「腹の中」に入れるもの、つまり「食べ物」の事でもあることもわかってきます。
この「食糧」を手に入れるには、「赤ままの花」の代表される植物のこと、植物の花粉を媒介させる虫たちのこと、それら花や虫を動かす「風のささやき」の存在、その「風」が運ぶ「匂い」の存在・・そういうものの存在に気がつかざるを得なくなってゆきます。そういうものの存在が、「腹の足し」になるものを育てていることについて。
そして、そのことを意識できる位置に立つことになってはじめて、この詩が、人間のことしか視野に入れずに書かれていたことに気がつきます。世界の「わ(環)」を見つめようとしていないことについて。
ふりかえってみると、わたし自身、そもそも「赤ままの花」のことなど何も知らないのに、そんな「ひ弱な花」を歌うな、などいう「煽動句」を鵜呑みにしていたわけです。「赤まま」は「イヌタデ(犬蓼)」の幼年ことばで、花が「赤飯(あかまんま)」のように見えて、子どもたちが「赤飯」のままごとをするのに使っていたとされるもので、わたしなどは、野に咲く雑草のようにしか見えないこの花の実際の美しい姿も知らず、中野の詩に煽動されて、つまらない花だと頭から思い込んでいた記憶があります。
哲学者パスカルも「一本の葦」を「ひ弱な草」と見ていましたし、多くの知識人の「動植物」を見る目の貧しさに、わたしたちはずいぶん、間違った世界観を植え付けられて育ってきたものだと思います。
だとすれば、そして中野重治の詩「歌」に貧しさを感じるとするなら、それに対抗する「詩」を創造しなければならないということになります。しかし、そんな詩がどこにあるのかということになります。わたし自身まだ読んだことがなく、どこかに在って欲しいと願う詩集。何かサンプルを言えと言われたら、ゲーテの「神と世界」(『ゲーテ全集1詩集』潮出版、『自然と象徴』冨山房百科文庫、に収録)の様なものをあげるしかないような・・でも、その詩集もだいぶ違うような気もしていました。そういう詩集は、苦心の「日本語訳」で読んでも、日本語の手触りで感じることがなかなか出来にくいところがあったからです。
ならば、自分で創る試みをするしかないのではないか・・。
5「あやとり」との出会い
〇 そして「あやとり」という詩を構想されてきたというわけですか。でもなぜ「あやとり」というような子どもの遊びが、重要な言葉として選ばれていったのか・・。
●ものごとの「現れ」をとらえる言葉はたくさんあって、学生時代からさまざまに教わってきたものです。そんな中でも、「すがた」「かたち」「イメージ」というあたりは、感覚的にはわかるのですが、とくに哲学由来の言葉としてある、「形相」「形状」「現象」「観念」「イデア」「エイドス」「表象」「対象」などといった言葉には、いつまでたってもよくわからない思いをしてきたものです。日常語としての根っこが実感としてつかめなかったからだと思います。
そのことは、ものごとの「現れ」を「詩」として表現する時にもわざわいとしてあって、どうしたものかと悩んでいたものでした。そんなとき、これまたよせばいいのに(能力もないのに)若いときの好奇心で「トポロジー」のようなものに興味を持つことがあり、野口廣(1925-2017)さんの本などを読もうとしていた時がありました。結局は、いつものように数式が出てくるあたりでよくわからなくなって、中途で投げ出していたのですが、わたしの領域である児童文化にかかわる子どもの遊びに、野口さんが触れているところだけにはなぜかずっと関心を持ち続けていました。それは彼が「国際あやとり協会」の会長や顧問をされているというところでした。高名な数学者である彼が、なぜ子どものする「あやとり」などに関心があるのか、当初はよくわからなかったのですが、いつしか自分なりに理解できるところが出てきました。それは、「あやとり」が、一本の糸を丸めて「わ」にすることから始まっていて、その「わ」が、実は「トボロジー」という学問に大きく関わっていたのだというところでした。それくらいまでは、わかってゆきました。
しかし野口さんは、子ども向けの「あやとり」の本を図入りでたくさん紹介されていたのですが、そもそも「あやとり」とは何だったのかという根本的なことには、まとまった研究を残されないままに亡くなられました。
あれだけすぐれた数学研究者でありながら、そして「あやとり」の重要性も十分にわかっておられながら、なぜ、その本性を究明されないままにこられたのか、と疑問でした。でも、わたしは私なりにわかっていったことがありました。それは、彼がトポロジーの数学研究者として相手にしていたのが、すでに「一本のわ」になったものだったということでした。どういうことかというと、彼にとって、「わになった紐」は、そこにすでにあるもので、誰が、なぜ、「結んで」「わ」にしたものなのか、という事までは、追求しないというものでした。そもそも「トポロジー」は、「つなぎ目」を問題にするのではなく、「つながっているところ」つまり「切ったり貼ったり」しないことが前提の領域の学問としてあったものでしたから。
そこからわたしは、野口さんの「あやとり」観では解明できないものがあることを意識するようになってゆきました。わたしが関心を持ったのは、誰かが、切ったり貼ったりしながら、それでも「一本のわ」になるようにつなぎとめている「あやとり」のことでした。そして、その後、この「一本のわ」を結んだり解いたりする「誰か」のことをきちんと考えるには、「誰かの手」を考えなくてはならないこともわかってゆきました。
それが、「生命」を「あやとり」として考えることの発想につながっていったわけです。そして、その発想が「手」の存在を考えない「トポロジー」と離れた瞬間でした。
ここから「あやとり」の「あや」についても、豊かな意味が見出せるということにも気がついてゆきました。(個人的には、レヴィ=ストロースが『蜜から灰へ』の中で、挿絵付きの「あやとり」を紹介し、高く評価していることへの驚きがあって、そこはもっと知りたいと思っているのですが、研究されている人を見つけることができていません。)
6 「あや」の発見
〇:「あやとり」と「あや」は別の次元のもののように思われますが・・。
●:すでに触れているように、ものごとの「現れ」を表す言葉の多くが、哲学用語の翻訳語や外来語、カタカナ語から来ています。そのために、詩を作る人たちも、ものごとの「現れ」を日常語で表現するには、とても不都合を感じていたと思います。先に述べた「形相」「観念」「イデア」「エイドス」「表象」などといった言葉はとうてい使えないからです。
そんな中で、わたしは「あやとり」に出会い、「あや」に出会いました。たしかに「あやとり」と「あや」は違っていて、「あや」を生み出すのが「あやとり」ですが、「あやとり」そのものも「あや」があってのことですから、両者はコインの裏表のような関係にあると思います。
古文で「あや」というのは、白川静『字訓』では「交叉することによって構成される模様、またそのような模様を織り出した絹織物をいう。木や玉などの表面にあらわれる自然の条理をもいう。」とされ。
広辞苑七版では、「あや【文・綾】」は
❶①物の面に表れたさまざまの線や形の模様。②入り組んだ仕組。ものの筋道や区別。③文章などの表現上の技巧。いいまわし。❷①経糸たていとに緯糸よこいとを斜めにかけて模様を織り出した絹。②斜線模様の織物。
とされてきました。「あやしい」という言葉も、おそらく「あや」の奇妙さを表すところから来ているのだろうと思います。広辞苑七版の「あやし・い 【怪しい】」の項目は、
「あや・し(シク)不思議なものに対して、心をひかれ、思わず感嘆の声を立てたい気持をいうのが原義。」とされ、①霊妙である。普通でなく、ひきつけられる。②常と異なる。めずらしい。③いぶかしい。疑わしい。④あるべきでない。けしからぬ。⑤(貴人・都人から見て、不思議な、あるべくもない姿をしている意)卑しい。身分が低い。粗末である。⑥えたいが知れない。不気味である。⑦なにかいわくがありそうである。⑧あてにならない。悪い状態に向かいそうである。なまめかしい、神秘的な、の意では「妖しい」とも書く。
と説明されていました。
これだけ見ても、この「あや」という言葉が日常語でありながら、豊かな中身を持っている事がわかります。ある意味では、日本の「根源語」のひとつといえます。
従来の哲学や精神医学の中からも、日常語を省みる試みは、いくらかは進められてきました。たとえば、「いき」(九鬼周造)、「ふれる」(坂部恵)、「甘え」(土居健郎)など。そんな中でも、たぶん「あや」は最も根源に迫る豊かな日本語であるのに、「あやとり」のような子どもの遊びに惑わされたのか、注目されてこなかったように思います。わずかに石牟礼道子さんの『あやとりの記』がタイトルとして使われてきたくらいでしょうか。
7 「生命」を「千手のあやとり」として考えること
〇:そこで、詩全体のタイトルに「あやとり」を選ばれたということに・・。
●: 「生命」の基本のイメージをどういうふうに考えるのかは、それぞれ研究者によって違いますが、わかりやすく考えるためにか、生きもののからだを「シート」のように考えようとしたり(『シートからの身体づくり』本多久夫)、「筒」のように考えようとしたり(『生きものは円柱形』本川達雄、『生命とリズム』三木成夫)されてきました。でも、「シート」と考えるにしても、「筒」と考えるにしても、それは「編み目」のように編まれていなくては機能しないわけで、そうすると、結局はどこかで、その「編み」の問題を考えざるを得なくなってゆきます。でも「科学」では、その「編み」は分子レベルの化学反応として説明できる部分があり、それを突き詰めてゆけば、編む「手」や「織姫」を考えなくてもいいということになります。むしろ、そんなものを考えることが、科学的に考えることの妨げになり、有害にしかならない、というふうに。
そうなると、そこで「手」や「織姫」のことを考えるのを諦めるか、奮起してあらためて「人文の発想」を見直そうとするか、試されるときが来ると思います。そこで「詩」も見直される次元がでてきたのではないかとわたしは考えています。